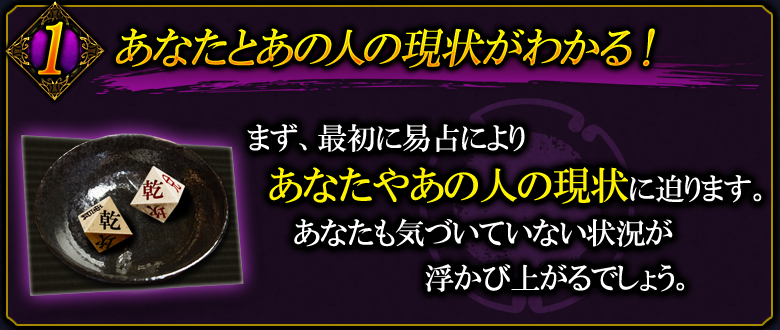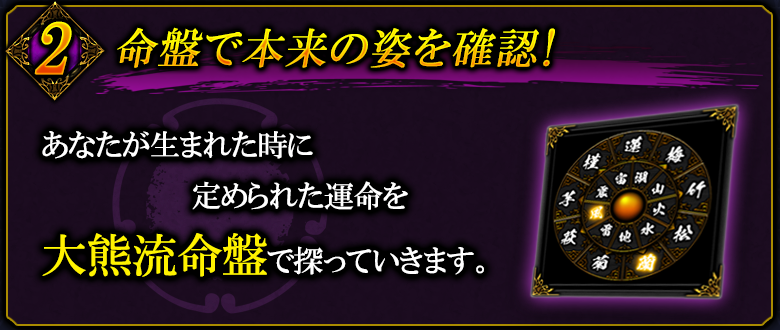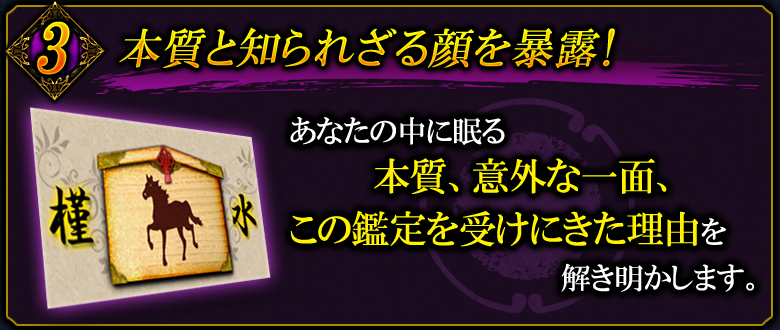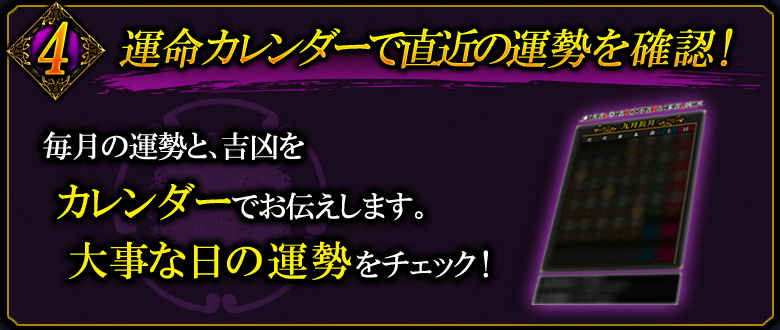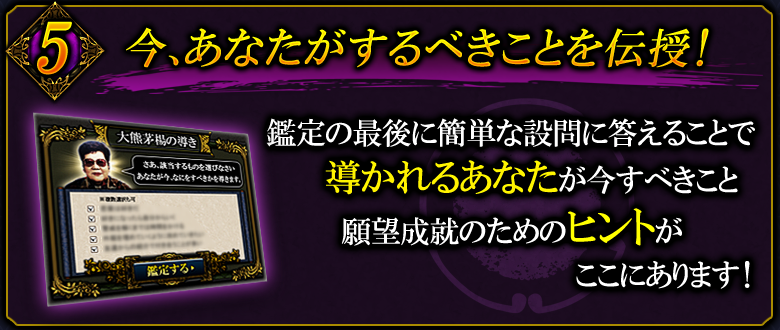TOP > 監修者紹介
監修者紹介
大熊茅楊(おおくま ちよう)
東京生まれ。「昭和の易聖」と呼ばれる加藤大岳に師事し、易についてを学ぶ。数々の占例を重ね、加藤大岳高弟の四天王の一人に数えられる。
昭和三十六年から五十三年まで実に十八年にわたり汎日本易学協会の機関誌「易学研究」に寄稿。後に出版されたが、女性が執筆したというのは極めて珍しく貴重。他に類をみない占例集となっている。
その後、昭和四十八年 日本占術協会創設に携わり、副会長を務める。日本作家クラブ理事就任。岳易館大熊茅楊教室主宰・茅楊会会長就任。
平成六年(1994年)六月五日逝去
著書に「春夏秋冬 易学占例集(東洋書院)」「ズバリ!病気は手でわかる(東洋書院)」「手相の見方―カラー図解(日東書院本社)」「図解 人相の見方―カラー版(日東書院本社)」「カラー版 血液型星占い―血液型と九星ですべてがわかる(日東書院本社)」などがある。
※本コンテンツは、日本占術協会の監修を受け、大熊茅楊先生の残されたお言葉や、資料を元に提供しております。
占術紹介
【易】とは
五十本の筮竹から一本を抜き取り、机上の筮筒の中に立て、これを太極とする。残り四十九本の筮竹を扇状に開き二分。掛肋器に掛けた中から一本取って、左手の小指と薬指の間に挟む。 左手と筮竹を八払いする。春夏秋冬と各二本ずつ四度取り出す。最後にあまりが出るので小指にはさんだ一本を加える。それが得られた卦の象数。
一本残り「乾」五本残り「巽」二本残り「兌」六本残り「坎」三本残り「離」七本残り「艮」四本残り「震」八本残り「坤」
左これを算木で上卦(外卦)として示す。これを再度行い、下卦(内卦)を示す。これで大成卦が出る。
つぎに、四十九本を左右に分け、右の一本を左の小指にかけ、左手の筮竹を六本ずつ数えていく。小指の一本を加える。一本残りなら「初爻」二本残りなら「二爻」三本のこりなら「三爻」四本残りなら「四爻」五本残りなら「五爻」六本残りなら上爻となる。 これが変爻(動爻)である。
筮竹で得られた上卦・下卦を算木を使って表示する。算木には陽と陰が分かるようになっており、それを見ながら占考に入る。
【大熊流命盤】
大熊茅楊オリジナルの命盤。外側に浮かび上がるのはその人の表層的な部分。内側に浮かび上がるのはその人の内面的な部分。その二つを用いる事で、鑑定している者の本質を導き出します。また、命盤で明らかになった二つの性質からその人を守護する存在も見えてきます。
100年伝説は伊達じゃない。ついに登場した占術協会開祖の鑑定はここが凄い!